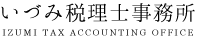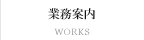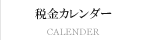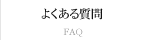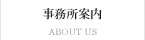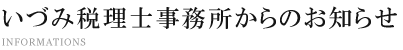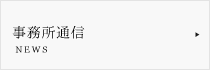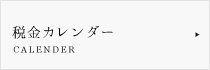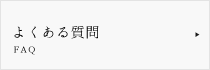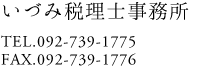2024/03/28
![]()
2024年2月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
2024/02/09
![]()
今年も、確定申告の時期が近づいてきました。
今回は、令和5年分の所得税確定申告の主な変更点をご紹介します。
Ⅰ.個人住民税の改正に伴う様式の変更
令和6年度の個人住民税から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式を、所得税と一致させることになりました。例えば、これまで上場株式等に係る配当所得について、所得税は総合課税、個人住民税は確定申告不要などと別々の課税方式を選択できましたが、これができないことになります。これにより、令和5年分以降用の所得税の申告書第二表の様式が一部変更されています。
〈令和4年分-変更前〉
〈令和5年分-変更後〉
(出典:国税庁HP)
Ⅱ.総合課税の対象となる者の改正
上場株式等に係る配当所得について、必ず総合課税となる者の定義が次の通り見直されました。
|
改正前 (R5.9.30までに支払を受ける配当等) |
改正後 (R5.10.1以降に支払を受ける配当等) |
|
発行済株式総数等の3% 以上を保有する個人 |
同族会社保有分と合算して発行済株式総数等の3%以上を保有する個人 |
これにより、仮に改正後に総合課税の対象となる配当が特定口座(源泉徴収選択口座)内で源泉徴収されていたとしても、総合課税として確定申告が必要となります。
Ⅲ.青色申告決算書等の様式変更
事業所得を申告する場合の青色申告決算書に、売上金額や仕入金額の明細を記入する欄が新設されました。
(出典:国税庁HP)
また、収支内訳書にある売上金額や仕入金額の明細欄に、登録番号(法人番号)の記入欄が新設されました。
以上、主な変更点になりますが、その他、納税地変更の届出書の提出が不要になったなど、細かい変更点もございますので、国税庁のHP等をご確認ください。
2024/02/09
![]()
2024年2月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
2024/01/23
![]()
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申しあげます。
さて、2024年度の税制改正大綱が公表されました。今回の改正では、さまざまな改正案が提出されていますが、その中でも身近な改正案をご紹介します。
◆2024年度税制改正大綱
Ⅰ.所得税・個人住民税の定額減税
(1)趣旨 賃金上昇が物価高に追いついていない中、国民の負担を緩和するため、令和6年分の所得税及び個人住民税の減額を行うというものです。
(2)適用期間 令和6年6月1日以後適用される予定です。
(3)内容
①所得税は、居住者の令和6年分の所得税額から控除されます。(その者の所得税額が上限) 本人3万円、同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円
②個人住民税は、納税義務者の令和6年度分の所得割の額から控除されます。(その者の所得割の額が上限) 本人1万円、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円
なお、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である者という所得制限があります。
Ⅱ.交際費等から除外される飲食費に係る見直し
(1)内容 交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から
除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人あたり1万円以下(現行5千円以下)に引き上げる。
(2)適用期間 令和6年4月1日以後適用される予定です。
Ⅲ.賃上げ促進税制(中小企業)
(1)内容
①中小企業の賃上げ促進税制に繰越控除制度が新設され、当期に控除できなかった税額控除の額を5年間に渡って繰り越せるようになります。
② 教育訓練費を増加させた場合の上乗せ要件が緩和されます。子育てサポート、女性の活躍推進に積極的に取り組んだ企業に対する上乗せ措置が設けられます。
(2)適用期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度
Ⅳ.中小企業倒産防止共済事業に係る措置
(1)内容 中小企業倒産防止共済の共済契約の解除をした後に再契約をした場合に、解除の日から2年を経過する日までの間に支出する共済契約に係る掛金は損金算入ができなくなります。
(2)適用期間 令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用される予定です。
Ⅴ.事業承継税制 特例承継計画等の提出期限の延長
(1)内容 事業承継の検討が遅れている状況を踏まえ、個人事業承継計画・特例承継計画の提出期限を2年延長し令和8年3月31日までとする。(改正前は令和6年3月31日まで)。
(2)注意 計画の提出期限は延長されましたが、特例措置の適用期限は延長されていないので注意が必要です。
Ⅵ.住宅ローン控除(子育て世帯等に対する措置)
(1)内容 縮小予定の住宅ローン控除について、子育て特例対象個人が認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額を次のとおりとします。
|
住宅の区分 |
借入限度額 |
|
認定住宅 |
5,000万円 (4,500万円) |
|
ZEH水準省エネ住宅 |
4,500万円 (3,500万円) |
|
省エネ基準適合住宅 |
4,000万円 (3,000万円) |
※借入限度額の()書きの中の金額は子育て特例対象個人以外の者の金額です。
(2)対象者 個人で年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって、年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者。
2024/01/23
![]()
2024年1月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。