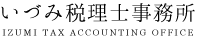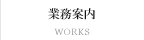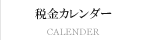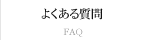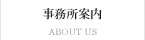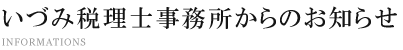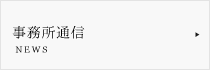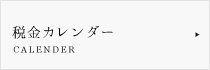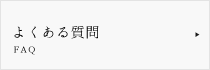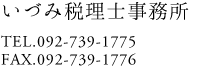2022/04/11
![]()
新年度の4月1日から、さまざまな法律や制度が変わりました。そこで今回は何が変わったのかを身近なものを中心にお知らせします。
◆2022年4月1日から変わったもの
1.民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました
民法改正で成人年齢が約140年ぶりに見直され、20歳から18歳に引き下げられました。また、婚姻年齢は男女ともに18歳以上に統一されました。成人年齢の引き下げにより、相続税、贈与税などに影響がでることとなります。
①未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合に、その未成年者に対し相続税が一定額控除される制度で、控除の額は未成年者が成人するまでの年数に10万円を乗じた額になりますので、今までと比べて控除できる相続税額が2年分(20万円)少なくなりました。
②相続時精算課税適用者の要件
原則60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度の適用を受けることができる者の年齢が、贈与の年の1月1日において20歳以上の者(令和4年3月31日以前)から18歳以上の者となったため2年早く適用が受けられるようになりました。
③事業承継税制に係る受贈者の要件
事業承継制度の適用に係る受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
④その他の贈与税
次の特例制度の適用に係る受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
イ.贈与税の税率の特例⇒直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は特例税率を適用するという制度
ロ.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置⇒
結婚・子育て資金に充てるために直系尊属から信託受益権の付与等を受けた場合に1,000万円まで贈与税を非課税とする制度
2.賃上げ促進税制の見直し(旧、所得拡大促進税制)
積極的な賃上げ等を促す観点から税額控除額が、大企業については最大30%、中小企業については最大40%に引き上げられました。
3.雇用保険料率
雇用保険料率は労使で以下のように変更になっています。
|
|
令和3年度 |
令和4年4月1日~ 令和4年9月30日 |
令和4年10月1日~ 令和5年3月31日 |
|
一般の事業 |
9/1,000 |
9.5/1,000 |
13.5/1,000 |
|
農林水産・清酒製造の事業 |
11/1,000 |
11.5/1,000 |
15.5/1,000 |
|
建設の事業 |
12/1,000 |
12.5/1,000 |
16.5/1,000 |
4.金融教育の導入
高校の家庭科の授業において、資産形成の視点に触れた金融教育が必修となります。
普段のお金の使い方から今後の長い人生を見据えた資金計画など、幅広く金融に関する知識や技能を身につけるのが目的とされています。
5.年金制度の改正
公的年金支給額が令和3年度に比べて原則0.4%引き下げられます。受給開始年齢は今まで60歳~70歳であったものが60歳~75歳に拡大されます(繰下げ受給の上限年齢引上げ)。また、65歳以上70歳未満で厚生年金に加入しながら勤務している場合に毎年1回年金額を見直す在職定時改定が導入されます。
6.育児・介護休業法の改正
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
7.道路交通法施行規則の改正
一定台数以上の白ナンバー車両を業務で使用する事業者に、運転前後の目視での酒気帯びの有無の確認、記録保存が義務化されました。
2022/03/31
![]()
◆賃上げ促進税制の見直し(※旧、所得拡大促進税制)
令和4年度税制改正では、中小企業の積極的な賃上げ等を促す観点から賃上げ促進税制について、適用期限が1年延長され税額控除率の上乗せ措置が見直されました。今回は、賃上げ促進税制ついてご紹介いたします。
中小企業向け「賃上げ促進税制」とは
青色申告を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
令和4年度税制改正での見直しの概要
中小企業については、現行の適用要件に変更はなく、税額控除率の上乗せ措置の見直しが行われます。これにより、中小企業においては、給与支給増加額などに対して最大25%の税額控除だったものが、最大40%に引き上げられる見込みです。
①雇用者給与等支給額が前期比で2.5%以上増加した場合は、税額控除率に15%が上乗せ
②教育訓練費の額が対前年比で10%以上増加した場合は、税額控除率に10%が上乗せ
※この上乗せ措置の適用を受ける場合、教育訓練費の明細を記載した書類の保存をしなければならないこととされています。(現行:確定申告書等への添付)
<改正による変更点>
※大企業向け賃上げ促進税制においては、適用要件が新規雇用者の給与等支給額から継続雇用者の給与等支給額に変更があったほか、継続雇用者給与等支給額が前期比4%以上増加した場合に税額控除率を10%上乗せできるようになります。(最大30%の控除)
※この内容は令和3年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。
< 編集後記 >
今回ご紹介した賃上げ促進税制については、中小企業庁のHPで「制度詳細については後日公開」となっておりますのでご確認下さい。
(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html)
ご不明な点がございましたら、当事務所担当者までお問い合わせください。
2022/02/22
![]()
◆事業復活支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業の継続回復を支援する「事業復活支援金」の申請受付が開始されました。今回は、事業復活支援金の概要や申請手続きについてご紹介いたします。
経済産業省「事業復活支援金」の概要
<給付対象>
下記、①・②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者*1
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の
売上高*2と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
*1 新型コロナウイルスの影響を受けたことについて、その裏付けとなる書類の追加提出を求められる場合が
あります。
また、以下の場合は給付対象外となりますのでご注意ください。
・通常事業収入を得られない時期を対象月とすることによる算定上の売上の減少
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで
単に営業日数が少ないこと等により売上が減少
※特例が適用される場合もあります。
*2 新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金・補助金等(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援
金、月次支援金、J-LODlive補助金等)は、各月の事業収入からその額を除きます。
ただし、対象月中に時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合は
「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象月の事業収入に加えます。
(給付額の算定においても同じ)
<給付額>
給付額 =「基準期間の売上」-「対象月の売上×5か月分」
※基準期間:「2018年11月~2019年3月」*、「2019年11月~2020年3月」、
「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
*月次支援金の基準期間より増えています
対象月: 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
<給付上限額>
|
売上高減少率 |
個人 事業者 |
中小法人等 |
||
|
適用した基準期間の 年間売上高 |
||||
|
1億円以下 |
1億円超5億円以下 |
5億円超 |
||
|
▲50%以上 |
50万円 |
100万円 |
150万円 |
250万円 |
|
▲30%以上50%未満 |
30万円 |
60万円 |
90万円 |
150万円 |
<申請の流れ>
① アカウントの申請・登録
経済産業省の事業復活支援金サイトより「仮登録(申請IDを発番)」をする
② 登録確認機関による事前確認の実施
登録確認機関から「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付
対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受ける
※当事務所は登録確認機関です。当事務所と「継続支援関係」に当たる方は事前確認を簡略化できます。
(継続支援関係:過去1年以上継続している顧問先)
③ 申請
マイページにアクセスし、必要事項を入力・必要書類を添付して申請を行う
※「一時支援金」「月次支援金」を受給された方は上記①②を省略、過去受給時の情報を活用することができま
す。
<申請受付期間> 2022年1月31日(月)~5月31日(火)
< 編集後記 >
事業復活支援金事務局HP「https://jigyou-fukkatsu.go.jp」で詳しい概要や申請手続きが行えますのでご確認ください。
ご不明な点がございましたら、当事務所担当者までお問い合わせください。
2022/01/12
![]()
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて、2022年度の税制改正大綱が公表されました。今回の改正では、さまざまな改正案が提出されていますが、その中でも身近な改正案をご紹介します。
◆2022年度税制改正大綱
Ⅰ.住宅ローン減税
(1)入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
(2)所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ。
(3)既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、
「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
(4)新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る)
(5)令和4年以降に入居する場合の措置は以下のとおり
①認定住宅等以外の場合
(イ)新築の場合
|
居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
控除期間 |
|
令和4年・令和5年 |
3,000万円 |
0.7% |
13年 |
|
令和6年・令和7年 |
2,000万円 |
10年 |
(ロ)既存住宅の場合
借入限度額2,000万円、控除率0.7%、控除期間10年
②認定住宅等の場合
(イ)新築の場合
|
|
居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
控除期間 |
|
認定住宅 |
令和4年・5年 |
5,000万円 |
0.7% |
13年 |
|
令和6年・7年 |
4,500万円 |
|||
|
ZEH水準住宅 |
令和4年・5年 |
4,500万円 |
||
|
令和6年・7年 |
3,500万円 |
|||
|
省エネ基準適合住宅 |
令和4年・5年 |
4,000万円 |
||
|
令和6年・7年 |
3,000万円 |
(ロ)既存住宅の場合
借入限度額3,000万円、控除率0.7%、控除期間10年
Ⅱ.賃上げ促進税制
(1)大企業向け
前年度から継続雇用している従業員の給与総額が前年度比3%以上増加した場合には雇用者全体の賃上げ額の15%を税額控除。また、前年度比4%以上増加した場合には25%の税額控除。
従業員の教育訓練費を前年度から20%以上増やした場合には控除率をさらに5%上乗せ。最大30%の控除となります。
(2)中小企業向け
新規雇用者も含めた雇用者全体の給与が前年度比1.5%以上増加した場合に、その増加額の15%を税額控除。また、前年度比2.5%以上増加した場合には30%の税額控除。
従業員の教育訓練費を前年度から10%以上増やした場合には控除率をさらに10%上乗せ。最大40%の控除となります。
※控除上限は法人税額等の20%。また、税額控除の対象となる給与等支給総額は雇用保険の一般被保険者に限られません。上記規定は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度から適用予定です。
Ⅲ.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が令和5年12月31日までと2年延長されます。非課税限度額は、
①耐震・省エネ・バリアフリー住宅のいずれかにあてはまる住宅であれば1,000万円
②上記以外の住宅であれば500万円となります。
なお、受贈者の年齢要件は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上となります。
2021/11/15
![]()
❖令和4年1月から改正電子帳簿保存法スタート
電子帳簿保存法とは、原則、紙保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件のもと、電子データによる保存を認める法律です。令和4年1月施行の改正で、帳簿書類の保存要件の緩和、電子取引の電子データ保存の義務化、罰則規定の強化がなされました。
その中でも、義務化により対応が必須となる電子取引ついてご紹介いたします。
1.電子取引における電子データ保存の義務化
電子取引において、現状認められている紙での保存が廃止され、電子データのまま保存することが義務づけられました。令和4年1月から紙での保存は「不可」となります。
2.電子取引とは
電子取引とは、以下のような「取引情報の授受を電磁的方法により行う取引」をいいます。
3.保存すべきデータとは
紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データです。
(例)請求書、領収書、契約書、見積書、注文書、送り状など
4.電子データの保存要件
①上記(3)検索機能の確保の簡易な方法の具体例
◆表計算ソフトを使用する方法
表計算ソフト等で索引簿を作成することで、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法です。
◆規則的なファイル名を付す方法
ファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約して、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法です。
②上記(4)改ざん防止措置について
◆システム費用等をかけずに導入できる“改ざん防止のための事務処理規定”については、国税庁HPでサンプルを公表しています。
③市販のソフトウェア等を使用して保存する場合
◆電子データ保存の要件に対応するソフトウェア等も販売されています。
◆要件を満たすかどうか確認するための認証制度及び相談窓口があります。
❖電子保存に2年の猶予
12月6日、政府・与党の方針で令和4年1月に施行予定の電子帳簿保存法について、2年間の猶予期間を設けることになりました。しかし、電子データ保存の義務化に変更はありませんので、改正電子帳簿保存法に対応できるよう準備していきましょう。
< 編集後記 >
今回紹介した制度については、「国税庁HP▶電子帳簿保存法関係▶電子帳簿保存法Q&A」にてご確認いただけます。
不明な点等がございましたら当事務所担当者までお問合せください。